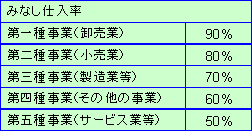難解な「簡易課税制度」
事業者が納める消費税を計算するに当たって、簡易課税という制度があります。
タックスアンサーに簡易課税制度を次のように説明しています。
|
|||||
みな仕入率を適用する場合の事業区分は、同じく国税庁のタックスアンサーで次のように説明しています。
簡易課税制度の事業区分の表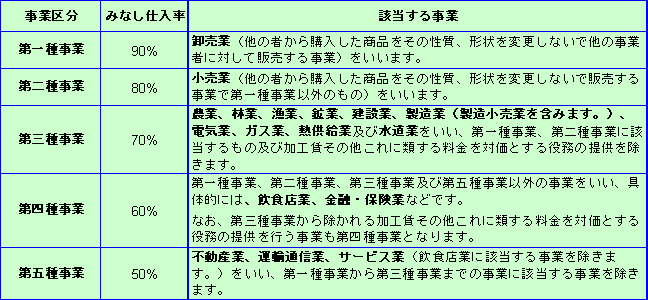 |
このタックスアンサーの説明には、少し解説が必要です。
まず第一に、「(課税売上高)×4%・・・」の4%の部分です。消費者は買い物をするときに5%の消費税を負担しています。この5%の消費税は、国税が4%、都道府県税が1%、合計で5%ということです。国税庁のタックスアンサーでは国税のことだけを解説するから4%で正しいわけですが、少々不親切だと感じるのは私だけでしょうか。
次が事業区分です。卸売業と小売業は「他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業」が同じです。違いは、販売する相手が事業者であるかどうかです。一般に考えられている卸売業と小売業の区別とは違いがあります。
この事業区分が「難解な簡易課税制度」といわれる所以です。
魚屋さんの例で考えてみましょう。魚屋さんが扱う鮮魚類の販売は、販売先が事業者であれば卸売り、一般消費者であれば小売りと販売先によって変わります。また、仕入れた魚をてんぷらや煮つけに加工して販売すれば第三種事業(製造業)とされます。
仕入れた商品を加工しないで飲食店や会社に販売・・・第一種事業
仕入れた商品を加工しないで一般消費者に販売・・・第二種事業
てんぷらや煮つけに加工して販売・・・第三種事業
業務用の車両を下取り販売・・・第四種事業
以上のように、売上の種類ごとに事業の種類を区分する必要があります。これを区分しないときはみなし仕入れ率の一番低いものとしなけれななりません。上記の場合では、区分していない売上を第四種事業として計算することになってしまいます。すなわち、納税額が多くなり事業者にとって不利な取り扱いです。
この場合、「軽微な加工」であれば、性質及び形状の変更がないものとして取り扱う。すなわち、卸売りまたは小売としてよろしいとされています。実は、この「軽微な加工」の判断が悩ましいものです。。
「軽微な加工」の例として次のものが挙げられています。
商品等に名入れ等を行い販売
仕入れたサッシとガラスを組立て規格品仕様のサッシ窓として販売
消火器の薬剤の詰替え
仕入商品を切る、刻む、つぶすなど
性質及び形状の変更があるとされるのは次のものです。
魚を煮魚、焼魚等加熱加工して販売
生しいたけを乾燥させて販売
荒茶を仕入れ、加工して製品茶にして販売
印鑑の製造販売
加熱処理、乾燥、塩漬けといった処理をすると製造と説明しながらも、「食肉小売店、鮮魚小売店において通常販売する商品に一般的に行われる軽微な加工(例えば、仕入商品を切る、刻む、つぶす、挽く、たれに漬け込む、混ぜ合わせる、こねる、乾かす等)を加えて同一の店舗で当該加工品を販売する場合には第二種事業に該当する。(国税庁「消費税質疑応答事例」より)」とされており、上記の魚屋さんの場合では、刺身や切り身に加工するのは「軽微な加工」に該当し、販売の相手によって卸売りや小売りの区別をします。
例を挙げればきりがありませんが、事業区分の判断がいかにに難しいかお分かりいただけると思います。そんなところから、私ども税理士の間で簡易課税と言わないで難解課税とい言う人もいるほどです。